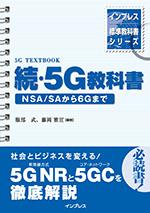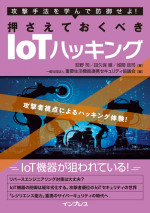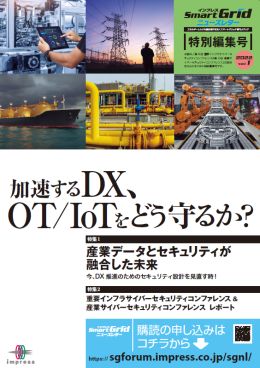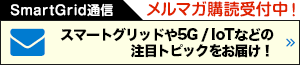政府の支援に求める情報共有の仕組みと継続性
新しい技術を普及させるには、初期市場を創出するための強力な政策支援が不可欠になる。増川氏は、「グリーンイノベーション基金をはじめとした政府の支援策の課題感」について質問を投げかけた。
積水ソーラーフィルムの森田氏は、「NEDOのグリーンイノベーション基金の支援は事業化を目的に顧客側も巻き込んだ取り組みとなっており、大変有り難い」と話す。民間として、「世界での競争という観点では、競合相手も様々な仕掛けを用意してくる。そうした動向や課題を国内で共有する必要がある」(森田氏)とし、国内のサプライチェーンが一体となる必要性を説く。
パナソニックの金子氏は、「企業としては事業の収益を確保する必要がある。政府の政策と協調しながら、市場を創造していくことが重要になる」とし、やはり、「そのための課題共有が不可欠だ」と述べる。
エネコートテクノロジーズの加藤氏は、「以前のシリコン太陽電池の時は、その支援に長期的な観点が欠けていたという反省もあるはずだ。政権交代などによって変わらない、継続的な支援の仕組みが長続きすることが重要だ」と指摘する。
2030年に向けた技術開発のスピード感:中国との競争
東京理科大学の植田氏は、「技術開発と量産が成功すれば、日本の勝ち筋が見てくる」とした上で、各社に「技術開発をどのようなスピード感で進めているのか」と問うた。
積水ソーラーフィルムは、2030年までに1GW(ギガワット)を生産するという目標を設定している。同社の森田氏は、「それまでにコストを下げ、シェアと奪われないようにする必要がある。そのために、まず大量生産でき、低価格で提供できる領域に注力する」と話す。
パナソニックの金子氏は、「皆さんが気になるのは、中国にどう勝つのかという点ではないのか」と切り出し、「パナソニックは、シリコン太陽電池で痛い目を見てるため、同じ轍を踏まないことが重要になる」と自戒する。ペロブスカイト太陽電池の特徴は、従来の発電効率の競争だけではなく、多様な用途に展開できる点にあると説明。それらの両立は、「技術側からするとハードルが結構高い」(金子氏)と本音を漏らしながらも、「そこに取り組むことこそが、中国との差別化要因になる」(同)との認識を示した。
政府は、2030年までに発電コストを14円/kWh注6にするという目標を設定している。この目標について、加藤氏は、「相当大変な数値」とみる。一方で、政府が設定している「2040年までに累積20GW」注7という導入目標に対しては、「グローバルでテラワット(1TW = 1000 GW)単位の議論がされる中で、累積20GWは小さいと感じてしまう」と言う。国内目標の達成は当然としつつも、よりグローバルな視点での野心的な展開が必要だと示唆した。
耐用年数20年以上に向けた各社の挑戦
実用化に向けて重要になる指標の1つが「耐久性」だ。シリコン太陽電池が20年以上の耐用年数を保証する中、ペロブスカイトがどこまで迫れるのかが、普及の鍵を握る。
NEDOは、グリーンイノベーション基金の中で、2025年度中にペロブスカイト太陽電池の寿命を20年にするという目標注8を設定している。この目標に対し、「目処が立っている」と語るのは、積水ソーラーフィルムの森田氏だ。ただし、「加速試験での見通しであり、実際の屋外環境でどうなるかは、これからしっかり見ていく必要がある」(森田氏)と慎重な姿勢も示す。森田氏は、「最終的には、発電コストの勝負になる。設置コスト、耐久コストも含めてシリコン太陽電池に勝てるようにしたい」と目標を語った。
金子氏も、「パナソニックは開発当初から信頼性を重視し、材料を選択するなどしてきた。20年保証というベースラインにいかに近づけるかが今後のテーマだ」とした上で、「見通しは立ちつつある」と述べる。
加藤氏は、別の視点を提示する。「用途ごとに求められる耐用年数は全く違う。車載であれば20〜30年は不要だし、数年で十分という用途もある。それぞれに適した耐用年数のものを提供できれば、ビジネスとして成り立つ」と見解を示す。
過去を糧にした「日本の勝ち筋」(ロードマップ)とは
シリコン太陽電池の時代に、かつてに日本が太陽電池市場を国際的にリードしながらも、価格競争の末に中国企業にシェアを奪われた。その苦い経験から、「ペロブスカイトで同じ轍を踏んではならない」という危機感は、登壇者全員に共通する。中国をはじめとした各国との技術開発競争が熾烈になるなかで、JPEAの増川氏は、「海外企業にどう勝てばいいのか」と問題提起する。
森田氏は、「従来の失敗は技術だけをサポートして、結局各メーカーがバラバラだった」と指摘する。経済産業省が進めるサプライチェーン協調の枠組みを活用し、「原材料から装置、モジュール、施工までをきっちり繋げて、日本のパッケージみたいな形で戦っていけないか」と提案する。さらに「理想は、海外に展開する時もみんなで行く形が理想だ」」と述べ、国内企業が連携して海外に製造拠点を築く提案もする。
金子氏は、この考えに同調し、「我々が対象とする建材サプライチェーンは、日本のハウスメーカーが強いように、これまでの太陽電池とは全く違う。エネコートテクノロジーズ社のように自動車メーカーと組むなど、それぞれのサプライチェーンの中で競争力を構築することが重要である」(金子氏)と語る。
加藤氏は、スタートアップの視点から、より現実的な戦略を語る。「メガソーラーのような終わりなき価格勝負の市場では、勝ち目はない。ペロブスカイト太陽電池には様々な用途がある。車載や低照度など、ニッチであってもトップを取れる市場を組み合わせ、トータルで勝てればいい」(加藤氏)。
2030年に向けた野心と展望
最後に、各社の目標が語られた。
森田氏は、「積水ソーラーフィルムは、ペロブスカイト太陽電池に100MWまでの投資を決定している。2030年に向けて、年間生産1GWに挑戦していく」と明言する。
金子氏は、「パナソニックは、2026年度から試験販売をスタートする」と計画を明らかにし、2030年の目標については「決まった事実はない」と前置きしつつも、「グリーンイノベーション基金の目標である200MWの工場というのを視野に入れながら、スピード感を持ってやっていきたい」と意欲を見せた。
加藤氏は、「現在の国内プレイヤーの情勢を見ていると、2040年に20GWという政府目標の達成は難しい。不足分をエネコートテクノロジーズが埋める。そのために、我々もGW級の構想を持っている」と野心的な目標を掲げた。
産官学が一体となり、かつてのシリコン太陽電池の失敗を乗り越えようとする熱い議論が交わされた今回の議論。ペロブスカイト太陽電池市場で日本の未来を照らさんとするメッセージを各登壇者が述べた。
注6、注7:いずれも経済産業省「次世代型太陽電池戦略」(2024年11月発表)に明記されている。
注8:NEDO「グリーンイノベーション基金事業/次世代型太陽電池の開発/次世代型太陽電池基盤技術開発事業/次世代型ペロブスカイト太陽電池の実用化に資する共通基盤技術開発」