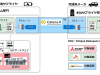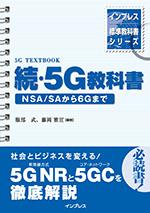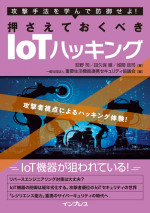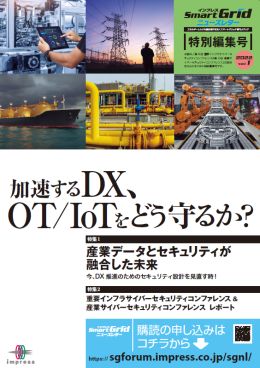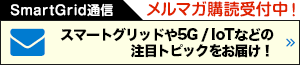日本で初めて商用化したコンテナ収容型液浸冷却システム
Quantum Mesh株式会社(以下、Quantum Mesh)は、データセンター向けコンテナ収容型液浸冷却システム「KAMUI」を、東京ビッグサイトで開催の「Japan Mobility Show 2025」(主催:一般社団法人 日本自動車工業会、会期:2025年10月30日〜11月9日)で2025年10月29日に報道公開した(写真1)。同システムは、コンテナ収容型液浸冷却システムとして日本で初めて商用化したという。
写真1: Quantum Meshのデータセンター向けコンテナ収容型液浸冷却システム「KAMUI」の外観
編集部撮影
空冷システムと比べ消費電力を10分の1に
AI技術の普及拡大を背景に、データセンターの消費電力量が爆発的に増えている。国際エネルギー機関(IEA)は、世界全体におけるデータセンターの電力消費量が2030年までに約9450億kWhとなり、2024年と比較して倍増すると予測する。
データセンターでは、サーバーを冷却するための空調機が膨大な電力を消費するようになっており、その省エネルギー化や代替が課題の1つになっている。さらに、サーバーの高出力化/高発熱化が進むことで、旧来の空冷システムでは十分な冷却環境を担保できないことが想定されているという。
KAMUIは、サーバーを直接冷却液に浸し、サーバーから発生する熱を吸収する「液浸」の仕組みにより、サーバーを冷却する。空調設備を使用しないことで、空冷システムと比べて消費電力を大幅に削減するという(写真2)。
写真2:KAMUIはサーバーを冷却液に浸して熱を移すことで冷却する
編集部撮影
Quantum Meshの試算によれば、冷却液の熱を吸収する素材として地下水を使用することで、従来の空冷システムと比較し、消費電力を10分の1に削減する。また、データセンター全体の電力使用効率を表す指標であるPUE(Power Usage Effective:)は1.03~1.04で、一般的な国内の空冷式データセンターのPUE1.50と比べて約32%の削減が可能だという。
主な構成は、サーバーを冷却液に直接浸し、熱を吸収する「液浸槽」、冷却液の熱を地下水や水道水などに移して除熱する「CDU(Cooling Distribution Unit:冷却水循環装置)」の2つである。それらを幅1200mm、高さ1400mm、奥行き800mmという大きさのコンテナ型の筐体に格納する。コンテナ収容型液浸冷却データセンターの商用化は国内初だという。
昨今、エッジコンピューティングの普及により、大規模なデータセンターよりも、現地でデータを処理する分散型のニーズが高まっており、コンテナ収容型を採用したという。関係者は、「従来のデータセンターは、建設工事や高圧電力の引き込みに非常に時間がかかっていた。コンテナ収容型であれば、地方などにデータセンターの小型版をスピーディーに作ることが可能できる」と説明する。
コンテナ収容型の特徴について、関係者によると、液浸冷却システムで使用する冷却液は消防法上の危険物ではないが、大量に取り扱うと各自治体の条例などに抵触する可能性がある。システムを規格化されたコンテナに格納することで、規制をクリアしやすくなる。
また、空調屋外機・室内冷凍機・空調機材などの設備が不要となり、設置面積を従来の5分の1mから3分の1に削減できるという。
コンテナ1台あたり、16Uまでのサーバーを運用でき、2Uのサーバーであれば8台設置が可能である。同社が運用する20フィートのコンテナ型データセンターはKAMUIを12台、2Uサーバ換算で96台収容可能である。
冷却液には、ENEOS株式会社が開発した「ENEOS IX Type-J」を採用した。同液は、可燃性物質を液体に近づけたときに着火する最低の温度(引火点)が250度以上になっているのが特徴だ。引火点が250度未満になると「消防法」上の「危険物」扱いとなり、届け出や施設の不燃化など規制が厳しくなる。また、透明無色にすることでサーバーの状態を確認しやすくしたほか、液体に配合する添加剤のバランスを調整して長寿命と絶縁性を両立させているという。
参考サイト
Quantum Mesh ニュースリリース 2025年3月10日、「Quantum Mesh データセンター向けの高効率な液浸冷却システム 『KAMUI』を独自開発、国内初※1の商用化へ」